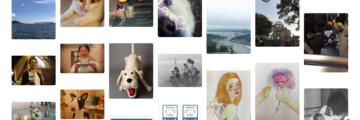Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
Warning: Array to string conversion in
/home/gardenjourna/gardenjournalism.com/public_html/wpGJ/wp-content/plugins/contact-form-7-modules/hidden.php on line
124
 左から、「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん、「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption]
左から、「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん、「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption] 「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん[/caption]
「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん[/caption] 「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption]
「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption] 「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん[/caption]
堀)
フェアであるというのは、すごくイノベーティブだと思います。吉本の話にも触れましたが、一方でメディアで取り上げてもいいかなと思うのは、フェアでないということが何かを殺しているのではないかと感じるからです。この映画でも描かれている「政権と市民社会」の関係にも、圧倒的にアンフェアな状況が見え隠れします。そうしたアンフェアな状況から、シリアでは内戦が始まり、2020年で10年目に入ります。依然として、昨日もシリアのイドリブ市に対して空爆がありました。圧倒的なアンフェアな状況の中で、人々が「それでも何かを変えなきゃいけない」と動いている。そういう中で、日本では選挙があっても投票率がすごく低いというのは、もっと世界の状況に目を向けられないかなと思いますね。ひょっとしたら気づいていないだけですごくアンフェアな状況の中で生きているのかもしれないという視点、足場を作る上でも、もっと海外の情勢に目が向くといいなと思います。だからこそ、メディアも奮闘すべきだと思いました。刺激を受けました。
「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん[/caption]
堀)
フェアであるというのは、すごくイノベーティブだと思います。吉本の話にも触れましたが、一方でメディアで取り上げてもいいかなと思うのは、フェアでないということが何かを殺しているのではないかと感じるからです。この映画でも描かれている「政権と市民社会」の関係にも、圧倒的にアンフェアな状況が見え隠れします。そうしたアンフェアな状況から、シリアでは内戦が始まり、2020年で10年目に入ります。依然として、昨日もシリアのイドリブ市に対して空爆がありました。圧倒的なアンフェアな状況の中で、人々が「それでも何かを変えなきゃいけない」と動いている。そういう中で、日本では選挙があっても投票率がすごく低いというのは、もっと世界の状況に目を向けられないかなと思いますね。ひょっとしたら気づいていないだけですごくアンフェアな状況の中で生きているのかもしれないという視点、足場を作る上でも、もっと海外の情勢に目が向くといいなと思います。だからこそ、メディアも奮闘すべきだと思いました。刺激を受けました。 左から、「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん、「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption]
左から、「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」プログラム部部長・馬野裕朗さん、「株式会社GARDEN」代表・堀潤[/caption]

 GARDEN 事務局
GARDEN 事務局